『鋼の自己肯定感「最先端の研究×シリコンバレーの習慣」から開発された”二度と下がらない”方法』(著者:宮崎直子)(かんき出版)とは―
自己肯定感がもともと低かった私が読んでみて、「これなら出来そう!」と感じた本です。
本の中の「やるべきこと」は明確でシンプル。
高い自己肯定感をキープするために具体的にやるべきことが書いてありました。
これなら、ずっと自己肯定感の低さに悩んでいた私にもできるかも!と思いました。自己肯定感の低さに悩んでいる人に読んでもらいたい本です。
著者 宮崎直子さんについて
著者の宮崎直子さんは、シリコンバレー在住。アラン・コーエン氏のもとでホリスティックライフコーチのトレーニングを受けた認定ライフコーチ。
現在は「鋼の自己肯定感を育てる講座」を展開されています。
この本が初めての著作です。
「鋼の自己肯定感」本の概要
この本では自己肯定感を一定に保つためにやるべき2つのポイントが書かれています。
- 自己肯定感とは何かをしっかり定義すること
- 鋼の自己肯定感を持つと決意すること
この2つのことをやれば、「鋼の自己肯定感」が手に入ると筆者は書いています。
それ具体的な内容はこのあと解説していきます。
<1>自己肯定感を定義する|「自己肯定感」ってそもそもなに?

この本の中では、繰り返し言われていることはー
自己肯定感、自己有用感、自己効力感を混ぜて考えないことが大事
3つの言葉はこんなふうに定義されています。
自己肯定感とは…ありのままの自分を無条件に愛すること
自己有用感とは…「自分はだれかの役に立っている」という気持ちのこと
自己効力感とは…「自分は何かができる」という気持ちのこと本のあらすじ

自己肯定感と自己有用感、自己効力感との違いって何だろう
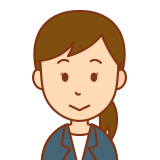
基準が自分にあるか、他者評価にあるのかというのが違いです
自己有用感や自己効力感を高めようすると、他人のために自分を犠牲にしてしまうことがあります。
そうならないように、まずは定義をしっかりとらえて考えましょう。
誰の役に立っていなくても、何もできなくても、つまり、自己有用感も自己効力感もゼロに近い状態でも、それでもそんな自分を受け入れて愛するというのが、本書で定義する自己肯定感だ。
(引用:鋼の自己肯定感「最先端の研究×シリコンバレーの習慣」から開発された“二度と下がらない”方法 著者・宮崎直子(かんき出版))

<2> 鋼の自己肯定感を持つと決意すること
2つ目のポイントは、「鋼の自己肯定感を手に入れる」と自分で決意することです。
ただそれだけです。シンプルに言い切っているところが、この本をおすすめする1番の理由です。
長いですが、本文を引用します。
何があっても折れない鋼の自己肯定感をどうやって手に入れるかについて、具体的なプランと方法をお伝えしておく。(中略)
「過去に何があっても、今どんな状態でも、未来に何があっても、私は私を受け入れ愛する。自分は一生自分に寄り添い、自分の親友になる」と決めてしまえばいいだけである。
鋼の自己肯定感「最先端の研究×シリコンバレーの習慣」から開発された“二度と下がらない”方法 著者・宮崎直子(かんき出版)
やることは「決めてしまう」だけ。
シンプルに言い切っているところが、この本をおすすめする1番の理由です。
これならできそうではないですか?
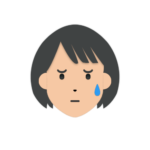
でも、自己肯定感を下げないなんて無理ないんじゃない
そう思うかもしれません。
しかし、この本でいう「鋼の自己肯定感」とは、絶対に自己肯定感を下げないということではないんです。
自己肯定感が下がりそうになったときに、いかに素早く気持ちを切り替えて自己肯定感が下がるのを食い止めるかできるか、ということが大事だと書かれています。
そのためのワークもしっかり本書に用意されています。
「鋼の自己肯定感」はとにかく「自分をありのまま受入れ愛するんだ!」と決めることで手に入る
感想
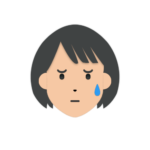
自分を好きになる、とか、ありがままを受け入れる、とか、それがいいのはわかるけど出来ないから困ってるだよ~
とずっと思っていました。
私のそんな気持ちに対して、自己肯定感を上げるためにやるべきことがしっかり具体的に書いてあるのがこの本の面白いと思った理由です。
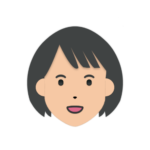
私の自己肯定感が低かったのは、私自身がで低いままでよしとしていたからなんだな
そんなことにも気づきました。
自己肯定感高いままキープすると決めてしまえばいい。
決めるだけなら、意外と簡単で、今すぐできることだと思いました。
この本は、最初にオーディブルの聴き放題プランで聞き、そのあと紙の本でも買いました。
タイトルが若干大げさな感じがするかもしれませんが、私はこの本読んで、ようやく自分の自己肯定感をキープできそうだと感じています。
自己肯定感が低くて悩んでいる人、ここまで読んでもやっぱり半信半疑な人に読んでもらいたい本です。
よかったら読んでみてください。
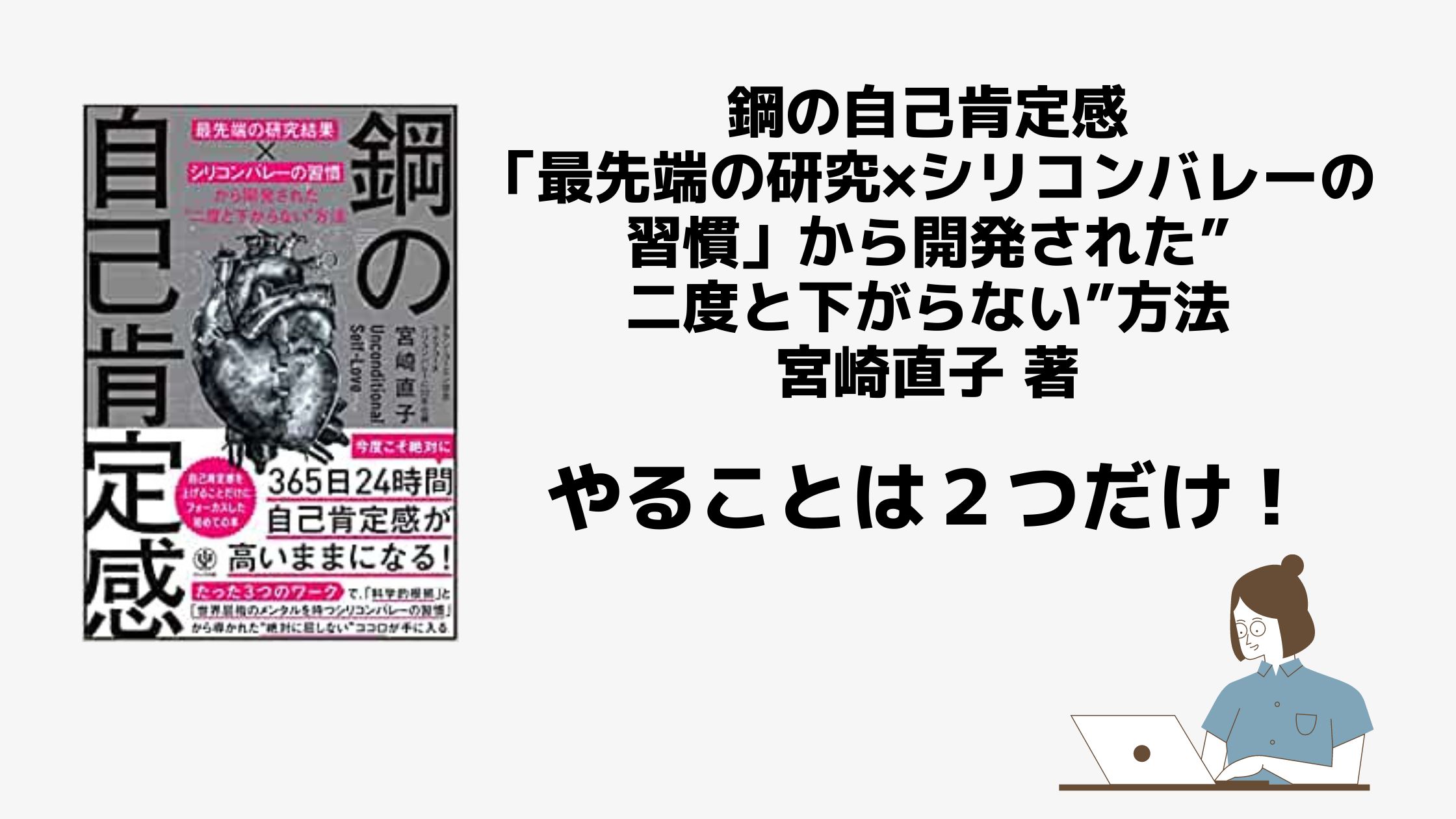


コメント